- 教員紹介
わたしの教育経営学研究-これまでとこれから / 木岡 一明 教授
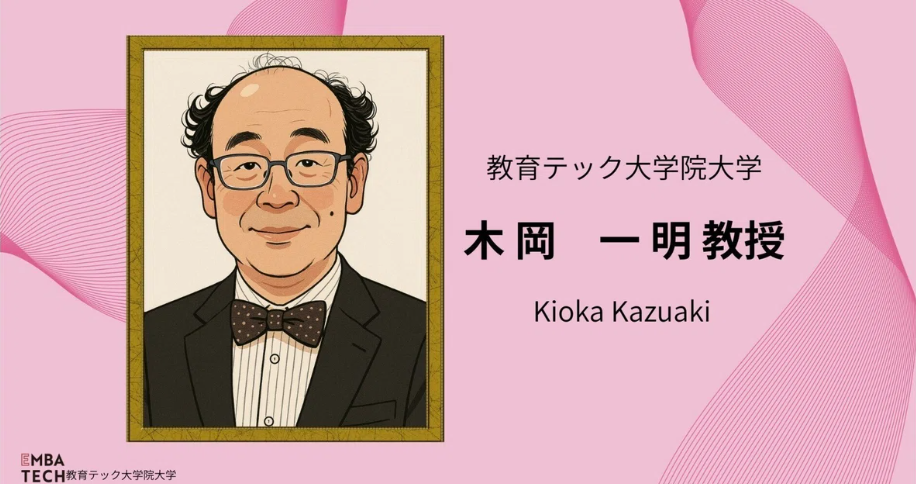
1.一期一会
校長先生でさえ学校評価をご存じない方がおられた頃(1979-80年)、わたしは京都教育大学で卒業論文「学校経営における学校評価の位置づけと改革の課題」を書いていました。研究動機は、中学生の頃から抱いていた漠然とした学校批判(不満)から、学校を変える力として「学校評価」が使えると捉えたことにありました。そこで、文献研究に加え、訪問調査による実態分析に取り組みました。インタビューでは、皆さん多忙ななかで、卒論生のために時間を割いて稚拙な質問に丁寧に答えてくださいました。しかし、傲慢にも、その頃のわたしは、そうした対応を当然のことのように受け止めていたのです。
大学院入学後しばらくして、卒論時のインタビュー調査に快く応じてくださった母校の先生が、過労のために亡くなられたことを知りました。
わたしは、その後もインタビュー調査を主要な研究方法としてきました。その調査の過程で、たくさんの先生方に出会ってきました。教師となった同窓生からも多くの刺激をもらってきました。そうした出会いと対話を重ねるにつれ、実践を対照できる批判を構成し、人々や学校で使ってもらえる研究でありたいと考えるようになっていきました。
2.温故知新と外見内知
大学院に入学した当時、心理学専攻だった学部時代の素養をもとに社会心理学や組織心理学を拠り所として理論研究を、と願っていました。しかし、ゼミ指導を受けて、結局、当時の「戦後教育の見直し」論議もあって、戦後教育改革当時の学校評価構想をまとめることになりました。ところが、論文の口頭試問会が始まるやすぐに、副査の先生が「なぜ、今や古色蒼然としている学校評価を取り上げるのか?」と詰問され、うまく説明できなかったことは、その後、幾夜かうなされる悪夢となりましたし、通史と国際比較へと導かれました。
歴史研究や国際比較研究を通じて、同じことが繰り返し論じられ、同じような試みが各地で展開していることを知りました。膨大な手引き書群が、歴史のなか(たとえば書庫の段ボール箱)に埋もれていました。
では、なぜ学校評価は定着してこなかったのか。それは、つづめて言えば、「学校の自己評価」という言葉が先行し「自己」評価の実体を不問のままに、スローガンでしかない「教育目標」の達成を評価目的にしてきたからです。その根底には、学校が経営目標下で協働する組織になり得ていない問題があります。だから、学校組織開発なのです。
国立教育研究所(現国立教育政策研究所)に移ってからは、「学校評価」の全国動向を実地に調査するとともに、各地のガイドライン作成に直接的に関わるようになりました。その実績によって、文部省(当時)の「マネジメント研修カリキュラム等開発会議」の協力者となり、浅野良一さん(当時、産業能率大学に在籍)と組んで、学校組織マネジメント研修カリキュラム・テキストづくりを担い、講習会や講師養成講座を担うことになりました。
名城大学に移り、「大学・学校づくり」を看板にして、大学・学校の経営専門職の養成にも携わるようになり、また名城大学の附属高等学校をはじめ私立学校(他県の高等学校や他の大学)にも関わってきました。
そんな状況において出会ったのが、ある教育センター次長の「怖いですねぇー、宗教ですねぇ」という一言でしたし、もう自律的に動くだろうと関わりを薄くした学校の後退し沈滞した姿でした。
3.電脳革新
本年4月から、自分がアナログ人間だと痛感しながら授業を担当してきました。スタッフの皆さんのお力添えで、何とか前期を終えることができました。
わたしが前期に担当したのは、「教育構想演習(Ⅰ)」というゼミだけです。後期には、「教育マネジメント論」をお手伝いすることになっていますが、主には引き続き演習を担当することになります。来年になるとさらに「教育政策論」を主に担当することになります。
前期のゼミでは、院生の皆さんの関心に基づく先行研究や学校経営にアプローチする手法に関する研究論文を読み込み、論理的な長文に慣れていただきながら、科学的な思考様式の修得に重点を置いてきました。後期のゼミでは、相対立する原理についての交通整理をもとに、事象を多角的に捉える思考を鍛えるつもりです。「教育マネジメント論」では、主に学校組織開発に関する理論的な説明を行ないます。「教育政策論」では、明治以降の歴史を辿りながら、国を起点とした公教育システムが、戦後改革を経ても長く維持されてきた経緯を跡づけ、民に足場を置いた公教育システムへの転換の機運が分権化改革以降、高まってきていることについて検討を加えたいと考えています。
本学の強みは、バックグラウンドの異なる教員と院生の皆さんが、論議を尽くした相乗効果の末に「新しい知」を創発できる点にあると思っています。こうしたことに興味があり挑戦したいとお考えの方々をお待ちしています。