- 院生紹介
「1EdTech技術標準」を推進したシステムづくり、データ利活用からの大学経営改善
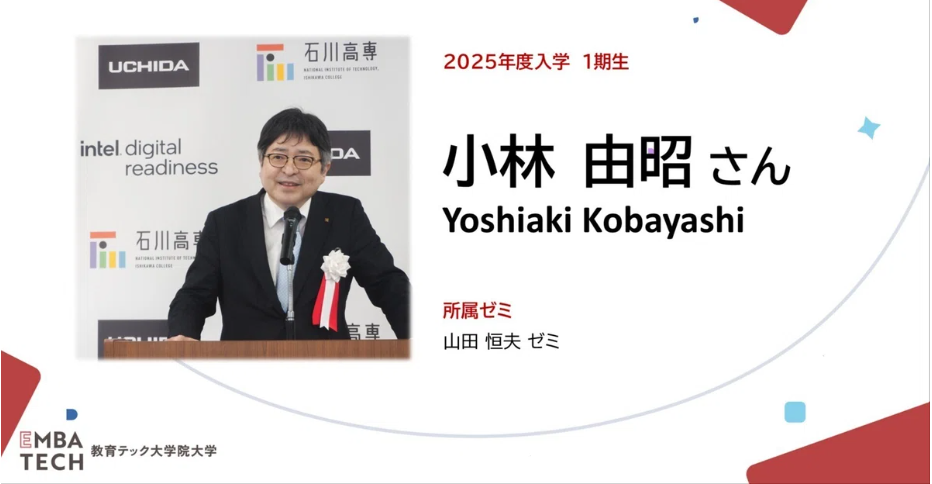
【教育イノベーター Voice1期生リレー連載 No.10】
「教育現場のテクノロジー活用の伴走者」として長年大学のICT導入と運用支援に携わってきた、 2025年入学1期生の小林 由昭さん。
現場で成果を上げながらも、「教育の質」と「大学経営」の両立という難題に直面し、実務だけでは答えきれない限界を感じたことが大学院進学のきっかけでした。
本記事では、1EdTech技術標準を軸に、教育デジタルエコシステムの社会実装を探究する研究や、大学院での学びがどのように実務を深化させているのかを紹介します。
目次
- なぜ、今この大学院で学ぶのか
- 学び始めて感じていること
- 取り組んでいる研究・活動やその面白さ
- 今後の展望、読者に伝えたいこと
- 入学後の生活スタイルの変化 ー1日の過ごし方/1週間の過ごし方ー
- 学習環境 ーオンライン受講、オンデマンド、課題の取組み方ー
- PROFILE
1.なぜ、今この大学院で学ぶのか
私は現在、株式会社内田洋行で執行役員 高等教育事業部長を務めています。大学におけるICTの導入支援や運用支援の販売・提供を通じて、教育や業務の質の向上を目指していくことが私の主な業務です。いわば、教育現場の「テクノロジー活用の伴走者」として、長年現場に寄り添ってきました。
ある大学では、最新のICTシステムを導入するプロジェクトを担当し、学生の学習成果が可視化され、教職員の業務効率も大きく改善されました。こうした現場での経験から、テクノロジーが教育に与えるポジティブな力を強く実感してきました。
しかし、近年の教育現場は人口減少、財政制約、デジタル格差といった複雑な課題に直面しています。今日の大学においては、単に「システムを導入する」だけでは、もはや不十分です。教育の質と大学経営の両方を見据えた“しくみ”をどうつくるか。その問いに、実務だけでは答えきれない限界を感じるようになりました。
そこで私は、実務経験を一歩引いて見つめ直し、学術的な視点とともに、より広い視野で「教育×テクノロジー×経営」を考えるため、大学院に進学することを決意しました。
2.学び始めて感じていること
入学前は、「実務の延長線上で、理論を補強できればいい」と考えていたところが正直ありました。しかし、いざ講義が始まってみると、その想像はすぐに覆されました。
一番驚いたのは、自分が“当たり前”だと思っていたことを、問い直す視点が養われたことです。
たとえば、ICTを導入すれば業務は効率化される、学びは豊かになる。そう信じて疑わなかった私に対して、講義の中では、「なぜそれがうまくいかないのか」「そもそも“効果がある”とは誰の視点か」といった問いが次々に投げかけられます。
この「問い直し」のプロセスこそが、大学院で得られる最大の価値の一つだと感じています。
3.取り組んでいる研究・活動やその面白さ
私の研究テーマは、「1EdTech技術標準を活用した教育デジタルエコシステムの社会実装」です。特に、日本の高等教育においてその普及をどのように進めていけばよいのかに関心を持っています。私の場合は実務と研究の方向性を合わせています。たとえば、LTI、OneRosterといった国際標準技術のシステムへの実装方法を確認したり、海外の大学の事例や同様の先行研究がないのか海外の論文検索をしたり、実務では得られなかった研究だからこその新しい気づきがたくさんあります。
必修科目の「教育テック総論」「教育テック事例研究」では、理論と自分の知識の範囲を超えた実践知を学べます。また、「教育データ・アナリティクス論」では、研究に必要となる因果推論を学ぶことができます。加えて、私は「教育マーケティング・広報ブランディング」や「教育テックのためのICT基礎」を選択履修していますが、講義内容を実務に照らし合わせて考えることで、とても有意義なものになっています。これらのすべてが、自分自身の 研究を深めることにおいても、実務においても土台になっているという実感があります。
それから、様々な面で先生に直接ご指導いただけることや、仕事の付き合いではない学友ができたことも社会人院生としての貴重な財産だと感じています。
4.今後の展望、読者に伝えたいこと
研究と実務を行き来しながら、私は「いい大学づくり」「いい教育づくり」を、ICTの力を通じて具体的に形にしていきたいと考えています。読者の方へお伝えしたいのは、「学び直しは決して遅くない」ということ。むしろ実務を経験してきた今だからこそ、問いが深くなり、学びによって世界が広がるという実感があります。
5.入学後の生活スタイルの変化
ー1日の過ごし方/1週間の過ごし方ー
働きながら学ぶ――これは想像以上にハードです。ですが、思考の“切り替えスイッチ”を持つことで、むしろ日々の生活が豊かになったように感じています。
【平日】
早朝:講義のオンデマンド視聴やレポート作成
日中:通常業務(提案活動、社内会議、外勤など)
夜 :帰宅後に1~2時間、講義のオンデマンド視聴やレポート作成
【週末】
土曜午前:講義のオンデマンド視聴やレポート作成
土曜午後:課題の執筆、文献リサーチ
日曜:できれば“休養”したいですが、講義のオンデマンド視聴やレポート作成をすることも。
6.学習環境
ーオンライン受講、オンデマンド、課題の取組み方ー
オンライン受講とオンデマンド配信を柔軟に使い分けています。普段は東京にいますが、出張先の大阪でオンデマンド受講をしたり、多忙な時期は講義にリアルタイム参加できないこともあります。録画によるオンデマンド視聴が可能なため、重要な部分を繰り返し確認でき、自分のペースで深く学び直すことができます。
課題に取り組む際は、メモアプリで思いついたことを記録しておいたり、生成AI(ChatGPTなど)を使って論点整理などしています。また、論文検索では講義の中で教えて頂いたアプリやツールを積極的に活用して進めています。アプリについては、ゼミの学友から最新のツールを教えてもらったり、使い方を助けてもらっています。
“仕事”と“学び”が互いに補完しあう感覚は、社会人院生ならではの醍醐味です。
7.PROFILE
株式会社内田洋行 執行役員・高等教育事業部 事業部長。文系学部を卒業後、同社に入社。CADシステムの営業を皮切りに、高等教育分野のICTシステムに約30年間携わる。
「いい大学づくり、いい教育づくり」を信条に、現場の声に耳を傾けながら事業を推進してきた。
現在は大学改革や教育DXの支援に取り組むほか、日本教育工学会(JSET)大会企画委員や某区の地域猫保護協力員など、社会貢献活動にも力を注いでいる。
所属ゼミ
山田 恒夫 教授 ゼミ