- 教員紹介
AIと教育者が共創する、好奇心から始まる学びのデザイン / 河﨑 雷太 教授
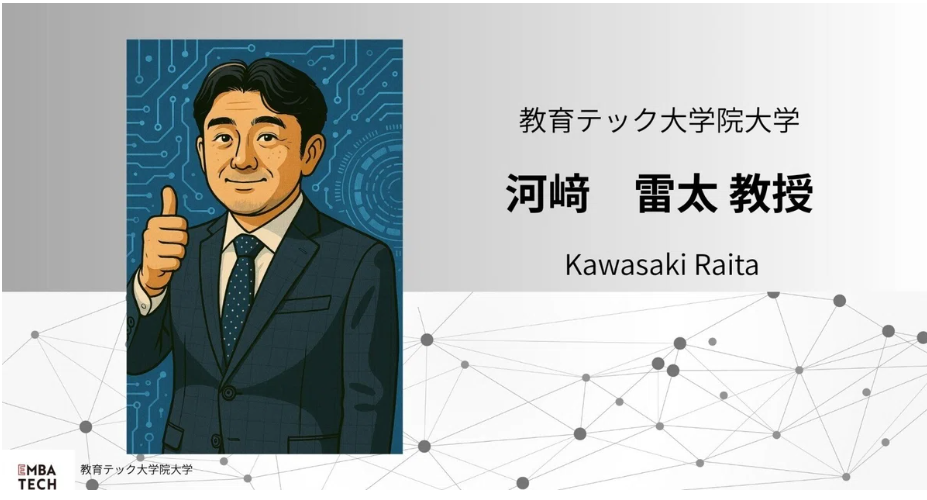
生成AIは「代わり」ではなく「共に成長を支える相棒」
最近、他人が夢中になる瞬間を、あなたは見たことがありますか?
私は、その「夢中」こそが学びの原動力だと考えています。
子どもの頃、私はプラモデルを作りはじめると、時間を忘れて没頭しました。夕飯に呼ばれても返事をせず、母に叱られるほどでした。
大学は工学部でバーチャルリアリティの研究を行い、モーションキャプチャを専門にしました。「模型の箱庭世界の楽しみを、コンピュータでもCGで再現できる」――そんな好奇心が研究の推進力でした。
そして今、教育に関わる中で強く感じるのは、人は“やらされて学ぶ”ときではなく、“知りたい・やってみたい”ときに最も成長するということです。その内側のエネルギー『好奇心』をどう発見し、どう学びへとつなげるか。
この問いに対して、生成AI(以降AI)は“代替者”ではなく、共に考え、共にデザインする相棒になり得ると考えています。
AIで「好奇心」を見つける
学びの出発点は、どの世代にも共通して“知りたい”という気持ちです。
自身の好奇心に気づいている学習者は幸せです。一方で、自身の好奇心が何か?どうすれば好奇心と学びを結び付けられるかを自覚できていない学生もちらほら見かけます。
学習者の言葉・行動をセンシングでき、かつ、作品・レポート・発言記録など多くのデータを倫理的・社会的な条件をクリアしてAIに入力できれば、AIは、それらを「抽象化」して整理し「メタ編集」することができます。
「この人は“なぜ?”と掘り下げる傾向がある」
「この人は“作りながら考える”タイプ」
など、好奇心の方向性を可視化できます。
教育者や上司は、それを手がかりに個々の学びを支援できます。
たとえば――
● 授業で頻繁に質問する生徒の傾向をもとに、探究テーマを提案する。
● 研修で実践を好む社員に、プロジェクト型課題を割り当てる。
AIが分析の中で見出した傾向は、単なる数値的な結果ではなく、教育者が対話や支援につなげるための“気づきの出発点”です。
教育者はそれを言葉と関係性の中で意味づける。
「あなたは探究型の学びが得意なんだね」「実際に動かして考えるのが好きなんだね」――
そう伝えられたとき、学習者の中に“自分の学び方”への自覚が芽生える可能性があります。
AIが構造を見つけ、人がそれを温かく表現し伴走者としての関係を築く。
そこから“自分ごととしての学び”が始まります。
AIで学びをつなげる(カリキュラムマッピング)
好奇心が見つかったら、その好奇心を満たす「学びの地図」に落とし込みます。
AIは、異なる分野や業務を横断的につなげることが得意です。
たとえば、学習者が「どうして光は曲がるのか」に興味を持ったとします。AIは理科(光の屈折)、数学(角度と比率)、美術(ステンドグラスや色彩)、さらにはデザイン思考(光の体験設計)まで関連づけて提案してくれます。
企業であれば、社員が「人の心を動かすプレゼン」を課題にしているとき、AIはマーケティング、心理学、ストーリーテリング、データビジュアライゼーションなど、学びのネットワークを描いてくれます。
教育者・上司はその地図を基に、チームやクラスの文脈に合わせて編集します。
ここで言う「編集」とは、AIが提案した学習計画を一から作り直すことではありません。 AIが個々の学習者に生成した複数の地図をまとめて俯瞰し、現在のカリキュラムや業務方針に合う“意味の方向づけ”を行うことです。
教育者や上司は、個別の詳細を見る代わりに、この“集合知マップ”を参照しながら、「今のクラスには共同探究を」「今の部署には小さな成功体験を」――といった方向づけの意思決定を行います。
AIが描く地図は完璧ではありません。 むしろ教育者が「これは今の学年に合う」「これは企業文化に合わない」と “人間の感性で意味を編み直す”ところに価値があります。
AIが描いた“構造”を、人が“物語”に変えていくのです。
AIは知をつなぐエンジン、教育者は意味を編む編集者。
その協働で、学びは現場の中で生きはじめます。
ゲーミフィケーションで「夢中の環境」をつくる
ゲームの世界では、「もう一回やってみよう」と思える瞬間がありますよね。 それは報酬ではなく、“あと少しで届きそう”という感覚。 教育でも、AIがその“あと少し”をチューニングしてくれる未来が見えます。
学びには、学習者が繰り返しトレーニングすることで体得するスキルが求められる時があります。
「繰り返し」を飽きさせない仕組みとして、ゲーミフィケーションが活きるでしょう。
教育のゲーミフィケーションでは、バッジ収集やリーダーボードで競い合うなど、インセンティブを期待する外発的モチベーションを導入したものが多いです。
それらも導入しつつ、私は人が“夢中”になるゲームメカニクスの導入を考えています。
ゲーマーが“夢中”になるときには、共通の条件があります。
よく利用されているゲームメカニクスに、フロー理論とアフォーダンスの視点があります。
フロー理論は、心理学者チクセントミハイが提唱した、
「人が完全に没頭できる状態」を説明する理論です。
スキルと課題の難易度が釣り合っているとき、人は最も集中し、幸福を感じる。
AIは、学習者の反応時間や成功率、再挑戦の回数などを解析して、難易度を動的に調整できます。
簡単すぎればチャレンジを、難しすぎれば支援を。
こうしてAIは、一人ひとりに『“ちょうどよい挑戦”を提供するチューナー』になります。

一方、アフォーダンスとは「環境が行動を誘う性質」のこと。
AIは教材や課題の中に“触ってみたくなる仕掛け”を埋め込めます。
たとえば、「このデータを少し変えたらどうなる?」
「他のチームの結果を組み合わせてみよう」――
そんな自然な誘いが、行動を引き出し、それは強制ではなく自分事の喜びになり内発的モチベーションが生まれます。
AIは、フローとアフォーダンスの原理を活かし、
学習者が自発的に動き出す環境を設計のアイデアを示せます。
自発的に、学ぶ学習者の姿勢を、教育者や上司は見逃さず、
「いいね」「その発想、面白いね」と温かく応答する。
「やりたい」と内発的モチベーションを持った学習者には付随でしかありませんが、その何気ない会話に、さらなる関係性・信頼性の構築があります。

教育者・上司がAIの結果に「意味」を与える
AIは学びの構造を示せますが、意味づけは人間の仕事です。
AIが分析した結果を見て、教育者や上司は、学習者と対話を重ねます。
「なぜそれに興味を持ったの?」「どんなときにやる気が上がる?」
そう問うことで、学習者は自分の学びの“物語”を語り始めます。
また、AIが提案する学びの構造を、現場のリズムに合わせて編集するのも教育者の役割です。
● 学校なら:「今日は成功体験を積ませよう」「来週はグループ探究にしてみよう」
● 企業なら:「今期は実践重視に」「次回は内省を中心に」
AIが理論を支え、人が感情とタイミングを調律する。
この共同作業によって、学びはデータから生きた経験へと変わります。
AIが点を描き、人がそれを線に、そして面に広げる。
そのプロセスこそ、未来の教育や育成の核心になるのだと私は思います。
おわりに ― AIと共に「幸せな学び」を社会へ
AIは、好奇心を発見するレンズであり、
学びをつなぐナビゲーターであり、
挑戦を調整するチューナーでもあります。
そして教育者・上司は、それを人の物語として紡ぐ編集者です。
ですが、児童・生徒の個人情報や、企業の業務情報など外部サービスである生成AIにインプットすることが倫理的・社会的に許されるか、ガバナンスの壁もあります。
その壁の条件を定め、乗り越えることができれば、AIが好奇心を見つけ、教育者がそれに意味を与え、学習者が自らの成長物語として学びに没頭する。この連鎖は、学校にも、企業にも、そして社会全体にも広がるはずです。
AIが人間を置き換えるのではなく、人間がAIと共に“幸せな学び”をデザインする時代へ。
その中で生まれる「夢中」は、年齢も立場も超えて、すべての学習者に通じる普遍の体験です。
あなたの教室、あなたの職場では、どんな「夢中の学び」が始まりそうですか?